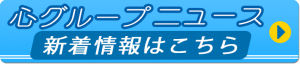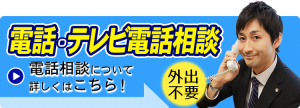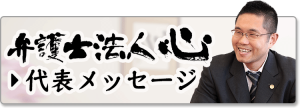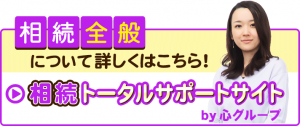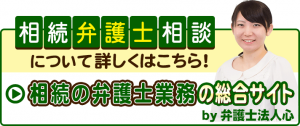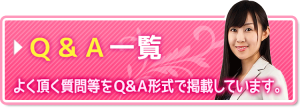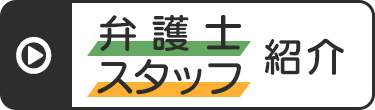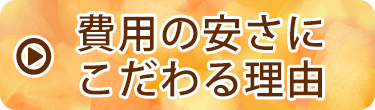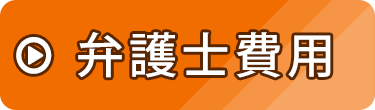相続放棄と債権者への通知に関するQ&A
- Q相続放棄をした場合、債権者に通知しないといけませんか?
- Q通知しておこうと思うのですが、どのようにすればよいですか?
- Q相続放棄をしたことについて、債権者から何か言われたりしませんか?
- Q弁護士に債権者への対応を任せることはできますか?
Q相続放棄をした場合、債権者に通知しないといけませんか?
A
相続放棄をしても、被相続人の債権者に通知をする法律上の義務はありません。
ただし、相続放棄をしたことは、通常であれば相続放棄を申述した方やその近親者くらいしか知りません。
実は相続放棄をしても戸籍謄本にその旨が記載されたり、公的機関に相続放棄の事実が共有されるということはありません。
そのため、こちらから債権者へ通知をしないと、被相続人の借金などを支払うよう請求がなされてしまう可能性があります。
なお、相続放棄の申述有無の照会という方法を用いて、債権者側から相続人が相続放棄をしているかどうかを調査する手段もありますが、債権者がこの方法を用いるのは、債権回収のために相続財産清算人の選任申立てをする場合などであると考えられます。
Q通知しておこうと思うのですが、どのようにすればよいですか?
A
被相続人のご自宅などに貸金業者などからの請求書がある場合には、まずはそこに記載された連絡先へ電話などで連絡をします。
そして、相続放棄をした旨を伝えるとともに、今後の請求を止めてもらうための手続きについて確認をします。
一般的には、相続放棄申述受理通知書の写しを貸金業者等の窓口へ送付することで通知は完了します。
Q相続放棄をしたことについて、債権者から何か言われたりしませんか?
A
債権者が自治体や貸金業者等の組織であれば、法定単純承認事由がないと考えられる場合には、相続放棄をしたことに対して何か言われることはほぼないと考えられます。
相続放棄には、初めから相続人ではなかったことになるという非常に強力な法的効果があります。
自治体や貸金業者等もこのことを理解していることが多いと考えられることから、相続放棄をした元相続人に対しての請求はすぐに打ち切ります。
債権者が知り合いなどの個人である場合には、感情的な側面もありクレームをつけられる可能性もあります。
それでも、相続放棄をした以上債務を返済する義務はありませんので、納得してもらうほかはありません。